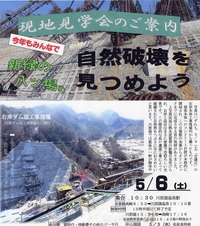2009年11月01日
ダム堤変更の真実 拙著転載・まえがき(二)
2004年12月、刊行の拙著『八ッ場ダムー足で歩いた現地ルポ』の「まえがき」
の続きを、さる10/5に転載の次の記述から、下記に記させていただきます。
今が紅葉のピークの吾妻渓谷。
ダム堤の位置が600メートルあがり、現在の位置に決まったことの真相には、以
下の事柄があります。
まさに、足を使って、当時の反対メンバーの方たちに伺った事実です。当時の反
対既成同盟の中枢の方たちしか知らない事実のようで、これが、交付金が吾妻町
に入ってしまうことに気がついた、反対既成同盟の知恵のようです。
年譜の上でも具体的には欠落させ、以下の記載のみ。
1973(昭48)年9月25日
反対既成同盟、ダム建設計画を変更し犠牲のない上流への陳情書
〃 11月14日 「自然環境を守る会」スタート
1975(昭50)年3月4日
ダムサイトの位置、当初計画より600㍍上流、戸数315戸に変更
そして、(前政権による)国交省は「いかに、環境政策に重きをおいている
か」の証明的に用いているのです。
http://www.ktr.mlit.go.jp/yanba/faq/q0/q0_4.htm
思い出せば、当時は、「八ッ場ダム」の名前の由来さえも、発足したばかりの市
民運動の間では、定かでありませんでした。
この八ッ場沢の写真が掲載なったのも、拙著が最初だったのではなかったでしょ
うか? 前回の転載と重なりますが、その部分から。
『八ッ場ダムーー足で歩いた現地ルポ』の「まえがき」(2004年12月刊)より
//////////////////////////////////////////
「八ッ場」と書いて「やんば」と読ませる特異なダム名は、ダムサイト予定地付近
の大字川原畑、字八ッ場の、この小字名に由来すると考える。吾妻川左岸には
「八ッ場沢」なる沢があり、吾妻川に垂直に注いでいる。場所は八ッ場大橋の手
前、ダム提建設予定地近くの一四五号線にかかる橋下の清流である。橋の欄干
の古びた石柱は文字面も欠損、磨耗していて読めない。語源には諸説がある。
思えば山には山の営みがあり、里には里の暮らしがあった。
人々はその村々の独自の地形に温められるように抱かれて、平穏に暮らしてき
た。
そうした最中の一九五二年、一方的にもたらされたダム建設の通告なのであった。
この間、明日の生活設計も立たぬままに水没民たちの多くは、自分の判断では
何一つ踏み出せずに、半世紀にわたりダムに翻弄され続けてきた。
特別措置法に基づく補償金は、犠牲者として当然の権利補償なのに、金銭の放
つ特有のくぐもりがアダとなって、下流の市民層とは、往々にして乖離させられてき
た。
突き詰めれば紛れもなく人権問題と呼べる。
不要不急の八ッ場ダムは、なりふり構わずの利権確保が優先。費用対効果は無
論、既設ダムの悪例が網羅された欠陥だらけの悪質公共事業の代表格である。
二一世紀は環境の世紀などと称されているのに、なぜこのダムが中断されず、今
日もまた一歩と着実に進展してしまうのかと、いらだちがつのってならない。
大義名分的に繰り出される治水・利水というよりも、八ッ場ダム半世紀の歴史は、
大物政治家の間で行きつ戻りつ揺れた、まさに政争と物欲の歴史と呼べる。
二〇〇一年六月の補償基準調印後、国土交通省の態度は一変し、水没住民の申
し出に対して、それまでのように直ちに駆けつけなくなったと聞く。しかも「お上のいう
ことに嘘はありますまい」と信じきってきた約束ごとのいくつかも、反故にされ出した。
それらははるか一〇〇年近くも前の谷中村の悲劇の構図に通じまいか。目見開き、
凝視すれば、まさに時代閉塞の状況が随所に見受けられる。
断崖の亀裂にも、物欲の歴史あり
そして、ダムには、外にも内にも翳りが多すぎる。
例えば、「耶馬"溪しのぐ吾妻峡」と親しまれてきた「名勝吾妻峡」(昭和一〇
年一二月文化財保護法指定区域に指定)のダムサイトの位置を、一九七三(昭和
四八)年に六〇〇メートル上流に変更し、今日に至る。
あまり知られてこなかったことだが、このこと一つを採り上げても、国指定遺跡
保存の美名とは裏腹に、内実はエゴと政治的判断に基づいていたことが浮かび
上がる。
現地に訪れ出した頃、「ありゃ本当は、税金が長野原町に入るようにしたんさ」
と当時の事情に通じていた方のさりげない一言があった。
当初の予定地であった鹿飛橋地点にダムサイトを設置すれば、確かに吾妻渓
谷は死滅する。けれども最大の理由は、そこが吾妻町の所有地であり、ダムによっ
てもたらされる固定資産税など様々な利益恩典が、犠牲となる長野原町ではなく、
川下の吾妻町に入ってしまうということにあったらしい。ために長野原町独占の公
算が大きく、賛否を超えた住民の共通項的な雰囲気が、底流にあったことは誰し
も一致する共通認識であった。
発端は闘争が熾烈だった一九六八(昭和四三)年頃に持ち上がったと聞く。
そもそもは「反対期成同盟」に連なる川原湯の反対住民が、反対だけでは運
動がいため、もっと広範に理解を深めるための戦術として、「吾妻渓谷ならびに川
原湯岩脈(臥龍岩・昇龍岩)を守れ」を前面に打ち出したものとの証言も得た。そ
の過程で、日々段階的にことが動き出したものと思われる。
しばらくの期間は混沌状態のままであったらしい。が、この動きを受けて翌年
一九六九年末には、文化庁は新ダムサイトの調査に当たっている。脆"い岩層の
欠陥が見つかり、極めて不適切な場所として指摘していたという。両脇に岩礁が
あり川幅も最狭なため、上流地点に比べれば工事費は安く、岩盤の質も応桑岩
屑なだれの堆積物だらけの一帯の中では比較的良好なことは、地元民ならば誰
でも知っていた。
ダムを造りたい建設省にとって、劣悪な諸条件はもともと承知のこと。だが、容
易になびかず持て余し気味の反対運動を切り崩す、その懐柔策に使えると踏む、
そんな思惑が働いただろうことも想像はたやすい。
なお当然ながら、ダム建設そのものを認めない市民活動家も含めた反対派の人
たちにとっては、移動しようとすまいと「絶対反対」の文字は揺るがず、一連の動き
は関係なく無関心であったそうである。
当時の動きを「八ッ場ダム年表」(一九八七年長野原町ダム対策課作成。その
後は年ごとのまとめを各戸に配布)から抜粋すれば、
① 一九七〇(昭和四五)・三・一八――「根本建設大臣は、国会において山口
代議士の質問に答えて、八ッ場ダムの調査や工事は地元の了解を得た上で
着工する方針だと答弁した」
② 同年三・二七――「反対期成同盟、約一〇〇人上京し、建設大臣に反対の
直訴状を提出」
③ 同年五・一八――「八ッ場ダム工事々務所は、吾妻渓谷のダムサイト予定
地附近の岩質調査のため、ボーリングを開始」
④ 一九七四(昭和四九)・一一・三〇――「文化庁『名勝吾妻峡の本質に及ぼ
す場合同意しない』河川局長宛」
⑤ 一九七五(昭和五〇)・三・四――「区長会議開催。ダム指定問題につき経
過説明(ダムサイトの位置、当初計画より六〇〇メートル上流、水没戸数三一
五戸に変更)」
決定されたという翌年の一九七四年になっても、なお文化庁は前記の懸念の通
達を出すに及ぶ。が、この半年近くも後に、長野原町では正式に区長会に諮ってい
る。
ダム提の上流変更に伴い、水没家屋が増えたことも記述から読み取れる。ことここ
に至って、文化庁も「及ぼさない」との判断を押しきられたのだろうか。
というわけで、“経費がかかろうが危なかろうが、ダムが造れさえすれば良い”
の方針が終息するまでに、少なくとも五~六年間の歳月が流れていたことなる。
なお、水没する川原湯岩脈の扱いについては、関係機関に問うと、二〇〇四年
の現在に至るまで、文化庁からの明確な伝達はないそうである。
ところがである。同じ一九七四(昭和四九)・一一・三〇の文化庁の対応について、
『長野原町町史・下巻』を繰ると、「昭和四九年十二月十四日付の上毛新聞では次
のように報じている」として次の記述となる。
昨年九月の衆議院予算委員会で、山口鶴男氏(社会党)が、安達文化庁長官
「文化庁は八ッ場ダムから吾妻渓谷を守るべきだ」とただしたのに対し、安達長
官は「ダムをつくる場合には、ダムサイトを上流に移して渓谷の本質を阻害しない
ようにしてほしい、と建設省に要望している」と答えた。
このため、建設省は安達長官の要望を尊重して、ダムサイトを当初計画より数
百メートル上流へ移動する計画を立て、そのための地質調査をしたいと昨年十二
月に文化庁に対して、文化財現状変更申請を出していた。文化庁では一年間か
けて検討を行い、一一月三〇日付で建設省に対し、国指定名勝吾妻渓谷内の
八ッ場ダム建設関連調査にOKを出した。
いかに地元紙とはいえ、ニュアンスの異なりにとまどいつつ、同一の事柄でも、
立場によって切り取り抽出する視点が異なり、微妙な差異が生じること。やがて、
文字化された文書が、正史として定着。瑣末なことながら、歴史の闇に埋没してい
く事実のあることを知った次第である。
そして三〇年近く経過した今日、往時の一般常識的な経過も脚色変容され、
国土交通省の刊行物ならびに公式発表では、「このため、名勝吾妻峡を最大限
残すために建設省(当時)は、昭和四三年より指定地の現状変更について文化
庁と協議を行い、昭和四八年に約六〇〇メートル上流の現ダムサイトに変更しま
した」と転化され出す。
これにて一件落着の趣で、昨今とみに環境問題に重きをおき出した、同省お得
意の大本営発表型の美談として位置が定まった感がする。
青葉の底に横たわる半世紀間の混沌とした複雑な推移とその襞は、この一例に
おいても、もはや部外者にはほとんど窺い知れない。
最も確実な事実経過は、反対期成同盟の主軸を担った方が生前、丹念に書き記
したという当時の記録、ご遺族保管という活動日誌の公開を待つしかない。その時、
空しく生を終えていった人々の、全身で権力と対峙し、怒りの汗を流し、無念の涙を
こぼした反対闘争の日々が、谷底からフワリと舞い上がるように、行間から如実に
よみがえって、思いの深さを語ってくれることだろう。
本当に、ダムには翳りが多すぎる。
国道一四五号線沿いにへばりつくように点在する家並み内部の、外部からは窺
うべくもない果てしない内輪の相克もまた、渓谷の断崖の深さに似ている。
恐らく鹿が飛べるほどの短距離で、その狭隘さが自然の洪水調節を果たしてき
たという鹿飛橋付近の麗姿に非ずして、吾妻渓谷の断崖にも、人間界の欲という名
のどみや亀裂が深々と幾重にも刻みつけられていることだろう。
(続く)
の続きを、さる10/5に転載の次の記述から、下記に記させていただきます。
今が紅葉のピークの吾妻渓谷。
ダム堤の位置が600メートルあがり、現在の位置に決まったことの真相には、以
下の事柄があります。
まさに、足を使って、当時の反対メンバーの方たちに伺った事実です。当時の反
対既成同盟の中枢の方たちしか知らない事実のようで、これが、交付金が吾妻町
に入ってしまうことに気がついた、反対既成同盟の知恵のようです。
年譜の上でも具体的には欠落させ、以下の記載のみ。
1973(昭48)年9月25日
反対既成同盟、ダム建設計画を変更し犠牲のない上流への陳情書
〃 11月14日 「自然環境を守る会」スタート
1975(昭50)年3月4日
ダムサイトの位置、当初計画より600㍍上流、戸数315戸に変更
そして、(前政権による)国交省は「いかに、環境政策に重きをおいている
か」の証明的に用いているのです。
http://www.ktr.mlit.go.jp/yanba/faq/q0/q0_4.htm
思い出せば、当時は、「八ッ場ダム」の名前の由来さえも、発足したばかりの市
民運動の間では、定かでありませんでした。
この八ッ場沢の写真が掲載なったのも、拙著が最初だったのではなかったでしょ
うか? 前回の転載と重なりますが、その部分から。
『八ッ場ダムーー足で歩いた現地ルポ』の「まえがき」(2004年12月刊)より
//////////////////////////////////////////
「八ッ場」と書いて「やんば」と読ませる特異なダム名は、ダムサイト予定地付近
の大字川原畑、字八ッ場の、この小字名に由来すると考える。吾妻川左岸には
「八ッ場沢」なる沢があり、吾妻川に垂直に注いでいる。場所は八ッ場大橋の手
前、ダム提建設予定地近くの一四五号線にかかる橋下の清流である。橋の欄干
の古びた石柱は文字面も欠損、磨耗していて読めない。語源には諸説がある。
思えば山には山の営みがあり、里には里の暮らしがあった。
人々はその村々の独自の地形に温められるように抱かれて、平穏に暮らしてき
た。
そうした最中の一九五二年、一方的にもたらされたダム建設の通告なのであった。
この間、明日の生活設計も立たぬままに水没民たちの多くは、自分の判断では
何一つ踏み出せずに、半世紀にわたりダムに翻弄され続けてきた。
特別措置法に基づく補償金は、犠牲者として当然の権利補償なのに、金銭の放
つ特有のくぐもりがアダとなって、下流の市民層とは、往々にして乖離させられてき
た。
突き詰めれば紛れもなく人権問題と呼べる。
不要不急の八ッ場ダムは、なりふり構わずの利権確保が優先。費用対効果は無
論、既設ダムの悪例が網羅された欠陥だらけの悪質公共事業の代表格である。
二一世紀は環境の世紀などと称されているのに、なぜこのダムが中断されず、今
日もまた一歩と着実に進展してしまうのかと、いらだちがつのってならない。
大義名分的に繰り出される治水・利水というよりも、八ッ場ダム半世紀の歴史は、
大物政治家の間で行きつ戻りつ揺れた、まさに政争と物欲の歴史と呼べる。
二〇〇一年六月の補償基準調印後、国土交通省の態度は一変し、水没住民の申
し出に対して、それまでのように直ちに駆けつけなくなったと聞く。しかも「お上のいう
ことに嘘はありますまい」と信じきってきた約束ごとのいくつかも、反故にされ出した。
それらははるか一〇〇年近くも前の谷中村の悲劇の構図に通じまいか。目見開き、
凝視すれば、まさに時代閉塞の状況が随所に見受けられる。
断崖の亀裂にも、物欲の歴史あり
そして、ダムには、外にも内にも翳りが多すぎる。
例えば、「耶馬"溪しのぐ吾妻峡」と親しまれてきた「名勝吾妻峡」(昭和一〇
年一二月文化財保護法指定区域に指定)のダムサイトの位置を、一九七三(昭和
四八)年に六〇〇メートル上流に変更し、今日に至る。
あまり知られてこなかったことだが、このこと一つを採り上げても、国指定遺跡
保存の美名とは裏腹に、内実はエゴと政治的判断に基づいていたことが浮かび
上がる。
現地に訪れ出した頃、「ありゃ本当は、税金が長野原町に入るようにしたんさ」
と当時の事情に通じていた方のさりげない一言があった。
当初の予定地であった鹿飛橋地点にダムサイトを設置すれば、確かに吾妻渓
谷は死滅する。けれども最大の理由は、そこが吾妻町の所有地であり、ダムによっ
てもたらされる固定資産税など様々な利益恩典が、犠牲となる長野原町ではなく、
川下の吾妻町に入ってしまうということにあったらしい。ために長野原町独占の公
算が大きく、賛否を超えた住民の共通項的な雰囲気が、底流にあったことは誰し
も一致する共通認識であった。
発端は闘争が熾烈だった一九六八(昭和四三)年頃に持ち上がったと聞く。
そもそもは「反対期成同盟」に連なる川原湯の反対住民が、反対だけでは運
動がいため、もっと広範に理解を深めるための戦術として、「吾妻渓谷ならびに川
原湯岩脈(臥龍岩・昇龍岩)を守れ」を前面に打ち出したものとの証言も得た。そ
の過程で、日々段階的にことが動き出したものと思われる。
しばらくの期間は混沌状態のままであったらしい。が、この動きを受けて翌年
一九六九年末には、文化庁は新ダムサイトの調査に当たっている。脆"い岩層の
欠陥が見つかり、極めて不適切な場所として指摘していたという。両脇に岩礁が
あり川幅も最狭なため、上流地点に比べれば工事費は安く、岩盤の質も応桑岩
屑なだれの堆積物だらけの一帯の中では比較的良好なことは、地元民ならば誰
でも知っていた。
ダムを造りたい建設省にとって、劣悪な諸条件はもともと承知のこと。だが、容
易になびかず持て余し気味の反対運動を切り崩す、その懐柔策に使えると踏む、
そんな思惑が働いただろうことも想像はたやすい。
なお当然ながら、ダム建設そのものを認めない市民活動家も含めた反対派の人
たちにとっては、移動しようとすまいと「絶対反対」の文字は揺るがず、一連の動き
は関係なく無関心であったそうである。
当時の動きを「八ッ場ダム年表」(一九八七年長野原町ダム対策課作成。その
後は年ごとのまとめを各戸に配布)から抜粋すれば、
① 一九七〇(昭和四五)・三・一八――「根本建設大臣は、国会において山口
代議士の質問に答えて、八ッ場ダムの調査や工事は地元の了解を得た上で
着工する方針だと答弁した」
② 同年三・二七――「反対期成同盟、約一〇〇人上京し、建設大臣に反対の
直訴状を提出」
③ 同年五・一八――「八ッ場ダム工事々務所は、吾妻渓谷のダムサイト予定
地附近の岩質調査のため、ボーリングを開始」
④ 一九七四(昭和四九)・一一・三〇――「文化庁『名勝吾妻峡の本質に及ぼ
す場合同意しない』河川局長宛」
⑤ 一九七五(昭和五〇)・三・四――「区長会議開催。ダム指定問題につき経
過説明(ダムサイトの位置、当初計画より六〇〇メートル上流、水没戸数三一
五戸に変更)」
決定されたという翌年の一九七四年になっても、なお文化庁は前記の懸念の通
達を出すに及ぶ。が、この半年近くも後に、長野原町では正式に区長会に諮ってい
る。
ダム提の上流変更に伴い、水没家屋が増えたことも記述から読み取れる。ことここ
に至って、文化庁も「及ぼさない」との判断を押しきられたのだろうか。
というわけで、“経費がかかろうが危なかろうが、ダムが造れさえすれば良い”
の方針が終息するまでに、少なくとも五~六年間の歳月が流れていたことなる。
なお、水没する川原湯岩脈の扱いについては、関係機関に問うと、二〇〇四年
の現在に至るまで、文化庁からの明確な伝達はないそうである。
ところがである。同じ一九七四(昭和四九)・一一・三〇の文化庁の対応について、
『長野原町町史・下巻』を繰ると、「昭和四九年十二月十四日付の上毛新聞では次
のように報じている」として次の記述となる。
昨年九月の衆議院予算委員会で、山口鶴男氏(社会党)が、安達文化庁長官
「文化庁は八ッ場ダムから吾妻渓谷を守るべきだ」とただしたのに対し、安達長
官は「ダムをつくる場合には、ダムサイトを上流に移して渓谷の本質を阻害しない
ようにしてほしい、と建設省に要望している」と答えた。
このため、建設省は安達長官の要望を尊重して、ダムサイトを当初計画より数
百メートル上流へ移動する計画を立て、そのための地質調査をしたいと昨年十二
月に文化庁に対して、文化財現状変更申請を出していた。文化庁では一年間か
けて検討を行い、一一月三〇日付で建設省に対し、国指定名勝吾妻渓谷内の
八ッ場ダム建設関連調査にOKを出した。
いかに地元紙とはいえ、ニュアンスの異なりにとまどいつつ、同一の事柄でも、
立場によって切り取り抽出する視点が異なり、微妙な差異が生じること。やがて、
文字化された文書が、正史として定着。瑣末なことながら、歴史の闇に埋没してい
く事実のあることを知った次第である。
そして三〇年近く経過した今日、往時の一般常識的な経過も脚色変容され、
国土交通省の刊行物ならびに公式発表では、「このため、名勝吾妻峡を最大限
残すために建設省(当時)は、昭和四三年より指定地の現状変更について文化
庁と協議を行い、昭和四八年に約六〇〇メートル上流の現ダムサイトに変更しま
した」と転化され出す。
これにて一件落着の趣で、昨今とみに環境問題に重きをおき出した、同省お得
意の大本営発表型の美談として位置が定まった感がする。
青葉の底に横たわる半世紀間の混沌とした複雑な推移とその襞は、この一例に
おいても、もはや部外者にはほとんど窺い知れない。
最も確実な事実経過は、反対期成同盟の主軸を担った方が生前、丹念に書き記
したという当時の記録、ご遺族保管という活動日誌の公開を待つしかない。その時、
空しく生を終えていった人々の、全身で権力と対峙し、怒りの汗を流し、無念の涙を
こぼした反対闘争の日々が、谷底からフワリと舞い上がるように、行間から如実に
よみがえって、思いの深さを語ってくれることだろう。
本当に、ダムには翳りが多すぎる。
国道一四五号線沿いにへばりつくように点在する家並み内部の、外部からは窺
うべくもない果てしない内輪の相克もまた、渓谷の断崖の深さに似ている。
恐らく鹿が飛べるほどの短距離で、その狭隘さが自然の洪水調節を果たしてき
たという鹿飛橋付近の麗姿に非ずして、吾妻渓谷の断崖にも、人間界の欲という名
のどみや亀裂が深々と幾重にも刻みつけられていることだろう。
(続く)
Posted by やんばちゃん at 23:24│Comments(0)
│八ッ場だより